FP3級受験体験記:30分前到着→学科57/60・実技満点。試験当日の動きと時間配分のコツ
はじめに
FP3級を受験してきました。結果は学科57/60、実技100点。その場で表示される速報ベースではありますが、まずは合格ラインをしっかり超えられた手応えです。この記事では、当日の動き(会場入り〜退出まで)と、実際に効果があった時間配分・見直しのやり方を、時系列で具体的に共有します。
FP試験は知識量も大切ですが、段取りとミスを減らす仕組みで得点が安定します。とくに「30分前到着」「開始可能になったらすぐ始める」「一周解き切ってから見直しに専念」という3点は、緊張しがちな本番でも再現しやすく、効果を実感できました。
本記事のゴールは次の3つです。
- 当日運用の実例:本人確認→ロッカー→着席→早め開始の流れ
- 時間配分の型:学科は「40分で一周+20分見直し」、実技は「30分で解答+見直しでケアレスミス拾い」
- 次への橋渡し:FP2級への学習の入口
この体験記は、これから受験する方が当日の不確実性(会場の動線や開始タイミング、休憩の使い方など)を減らし、得点の下振れを防ぐヒントになればという狙いでまとめています。では、持ち物と事前準備、そして会場入りの所作を順に解説します。
当日の準備
本人確認書類(原本):
運転免許証 または マイナンバーカード。ケースやカバーから即取り出せる状態に。
- 貴重品は最小限:本人確認書類だけを身に付け、スマホは電源オフ→ロッカーへ。
- ポケットの中身ゼロ作戦:入室直前にポケット空チェックを癖づけると、セキュリティ対応がスムーズ。
- 筆記用具:会場支給の指定筆記具(持ち込み不可)。
会場入り
当日の緊張を最小化するには、手順を“型”として持っておくのが一番。ここでは、実際の動線に沿って、声かけ例・確認ポイント・つまずきやすい箇所までまとめます。
受付・本人確認
- 受付列に並ぶ
案内掲示を確認し、指定の枠へ進みます。 - 本人確認書類を提示
運転免許証 or マイナンバーカード(原本)をすぐ出せるよう、手に持って待機。- スタッフが氏名・顔写真・生年月日を照合。
- マスク着用時は一瞬のマスク下げの指示があることも。
- スマホは電源オフ→ロッカーへ。バイブ・サイレントでも電源オフが無難。
- ポケット空チェック:ペン・メモ・イヤホンなどの入室不可物品が残っていないか、両ポケット+内ポケットを触って確認。
- 飲み物・軽食は休憩スペース用に。試験室内は不可。
試験室へ入室
- 入室時の最終確認
受験番号・氏名の再照合や、注意事項の口頭説明が入ることがあります。 - 指定席に着席
机上の案内・画面の指示(試験システムの操作説明)を確認。
学科試験
ここでは実際に行った「40分で一周 → 20分見直し」の運用を、手つきレベルで分解します。結果は57/60点。取りこぼしを最小化しつつ、30分ほどの余白を残した進め方です。
- 目的は“満点”ではなく“合格安全圏”:難問は深追いしない
- 配点は均等想定:迷ったら易問の取りこぼし防止を最優先
- 迷いを可視化:保留にした設問は一目で戻れる印をつける
(※CBTならフラグ機能)
40分で一周し切る
- 最初の5問は“助走”
- 取りやすい問題からテンポを作る。1問30〜45秒の目安で手を動かす。
- 迷ったら30秒で見切り
- 根拠が2つに割れる・思い出せない→即フラグして次へ。
- タイムチェック(10分刻み)
- 10分ごとに「何問まで進んだか」を確認。遅れは保留増やして前進で調整。
休憩の使い方
やったこと
- 水200〜300ml
やらなかったこと
- 重い復習や詰め込み(記憶の混線を招く)
- 学科の誤答の反芻(気持ちが乱れる)
- 甘い飲料の一気飲み(眠気の原因)
実技試験:短時間で解き切るコツ
今回の結果に直結したミニテク
- 「端数は最後」を徹底 → 中間で丸めず誤差ゼロ
- 赤意識ワード(税込/税抜、四捨五入、最も不適切)を見つけた瞬間に口パク
- 保留は2割以内 → 見直し時間で必ず刈り取れる規模に抑える
うまくいった
- 早め開始で静かな時間帯に集中できた。
- メモのレイアウト固定で転記・単位ミスを抑制。
- 見直しで1問のケアレスミスを回収。
うまくいった点
前倒し開始で“静かな時間”を確保
- 到着→手続き→30分前からの早期開始がそのまま集中力のボーナスに。
- 実技は開始20分前スタート。
- 時間配分の“型”運用
- 学科:40分で一周 → 20分見直し
- 実技:30分で解答 → 見直しで回収
→ 結果:学科57/60、実技100点。取りこぼし最小化を実感。
- 見直しの“機械化”
- チェック順序を固定:極性(正/誤)→単位→端数→マーク位置。
- 感情ではなく手順でミスを拾えた(実技でケアレス1問を回収)。
- 保留の上限管理(最大2割)
- 迷いを見直しに送る設計で、思考の渋滞を回避。
FP2級へのロードマップ
3級と2級の違い(押さえる軸)
- 知識の深さ:
3級=用語の“表札”を知る/2級=中身と境界まで説明できる。
例)「NISAがある」→2級は対象・上限・非課税期間・併用可否まで。 - ケース読解:
与件(登場人物・資産・目的・制約)から制度適用の可否と最適な選択を組み立てる思考が増える。 - 計算の重さ:
税・利回り・年金・不動産・相続評価など、手順の正確性と端数・単位の扱いがよりシビアに。 - 実技の選択制:
実技は主催団体や科目で形式が異なることがあるため、申込時の案内を必読(出題範囲・配点・電卓や筆記具の扱い等)。
まとめ
- 30分前到着→可能なら前倒し開始
待ち時間の消耗を避け、見直し時間を厚く確保。 - 時間配分の“型”を固定
学科は40分で一周→20分見直し、実技は30分で解答→見直し回収。 - 見直しは“機械化”
極性→単位→端数→マークの順で、感情ではなく手順でミスを拾う。 - 保留の上限管理(2割以内)
迷いは30秒で保留化し、後段で理屈優先で決着。
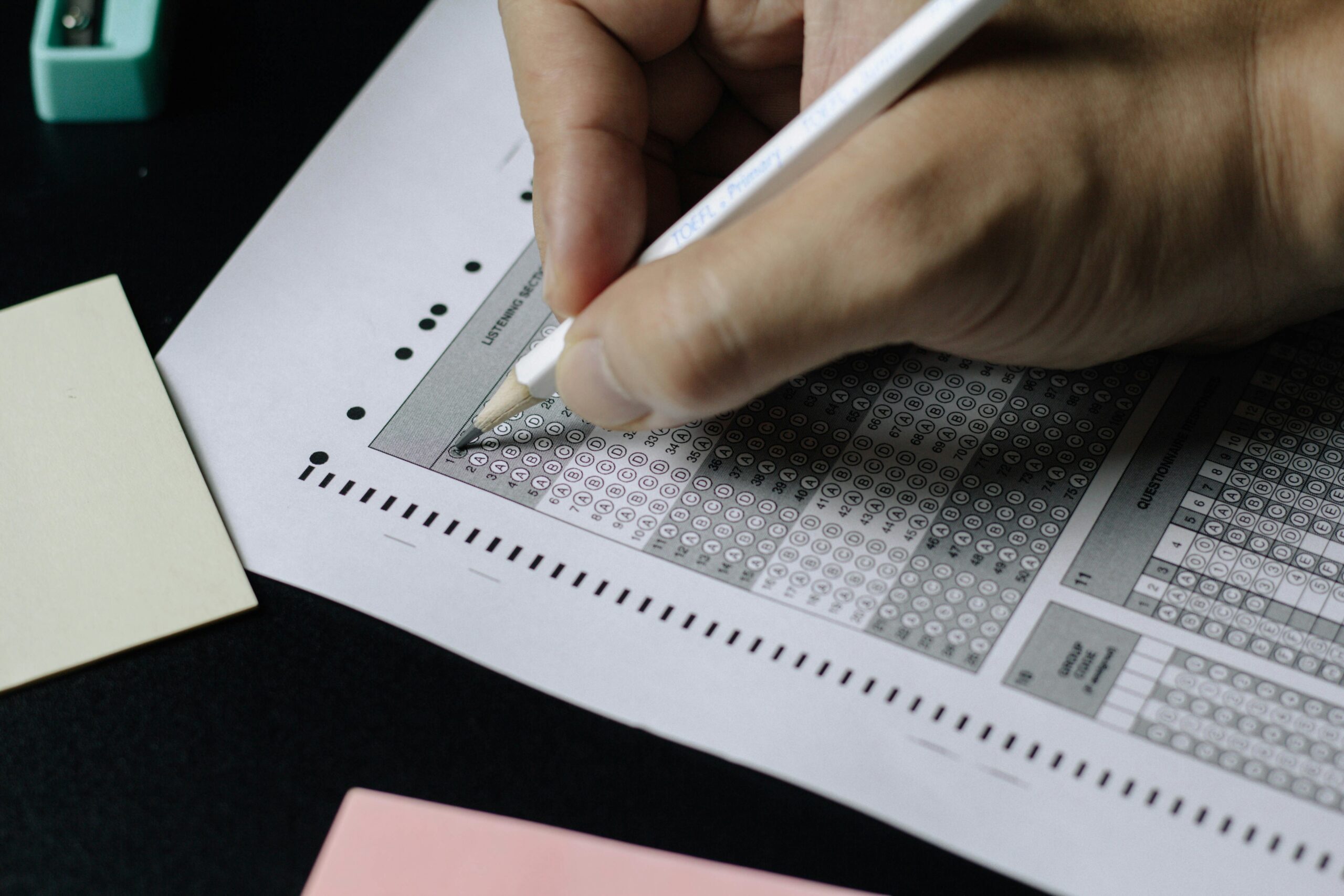


コメント